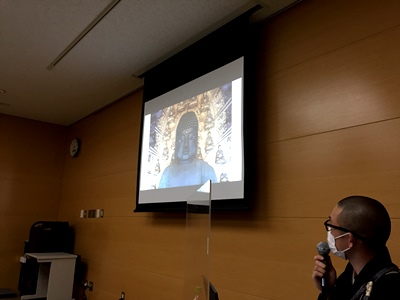奈良ひとまち大学授業の「奈良の『おいしい!』を飴にする~飴の専門店、ならBonbonって?~」に参加させて頂きました。
授業は、ならBonbonの創業者であり、お菓子研究家の神谷優希さんとスタッフの方との対話形式で行われました。

内容は、いかにしてお店を作り、飴を誕生させたかを、先生の人生観や思い・こだわりを交えて話して頂けました。
お土産用に頂いた「大和橘」の飴をはじめ様々な奈良ゆかりの飴があり、それぞれの生みの苦労やこれからの展望も話して頂けました。
瓶にもこだわりが。

個人的な感想ではありますが、商品自体やネーミングのこだわりだけでなく、やはり創業者としての強いビジョンや行動力にとても感銘を受けました。
今まで奈良になかったものに新たな奈良のエッセンスを加えて新しい奈良の魅力が生まれてきていることに、奈良の希望ある未来を感じました。
奈良市の方針に基づき、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、
また参加者および関係者の皆様の健康・安全を第一に考慮し、
開催予定の以下の授業を中止とさせていただくことになりました。
5月28日(金)18:30~20:00
かわいい奈良を文房具に
~coto mono流の奈良の魅力発信~
5月29日(土)13:00~15:30
若宮さんってどんな神社?
~春日大社の摂社、式年造替を迎える~
5月30日(日)14:00~15:30
奈良を記事にするということ
~新聞記者の仕事と奈良のこと~
※順延ではなく中止となります。
楽しみにしていただいていたところ、誠に申し訳ありません。
奈良ひとまち大学では、今後もみなさまのご期待に応えるような授業を多数開催していきたいと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
奈良ひとまち大学第401回の授業「大仏さんのふしぎ、発見! ~東大寺と大仏のあれこれ教えます~」に参加させていただきました。
今回の講師は東大寺大仏殿副院主の清水公仁先生。
「奈良県民なのに、今までそんなの知らなかった!」というような大仏さま造立にまつわるエピソードをたくさん聞くことができました。

驚いたのは、大仏さまはもともと東大寺に造られる予定ではなかったということ。
当初は近江の紫香楽宮に造られる計画だったけれど、方角不吉説(諸説あり)などのために、最終的に東大寺に造られることになったそうです。
そして、東大寺には地主の神さまがおらず、大分県の宇佐八幡宮の神さまに入っていただいた、というお話も面白かったです。
この時、八幡神さまは大分県から東大寺までお神輿で来られたそうですが、これがいわゆる日本のお神輿の始まりなのでは?という説があるそうです。
八幡神さまは転害門を通られたそうで、転害門が2度の戦火に見舞われたのにも関わらず無事だったのは、きっと神さまのお力なのでしょうね。

清水先生は毎年8月に行われるお身拭いで、大仏さまの螺髪部分を清掃するために大仏さまの頭上まで登られたことがあるそうです。
どのように登るかというと、大仏さまの背中にあるドアから内部に入り(大仏さまの中は空洞)、内部の木組みをジャングルジムのように登り、最後はマンホールから出るみたいに、螺髪をパカッと下から開けて外に出られるとのこと。
恐れ多いですが、一度体験してみたいものです。
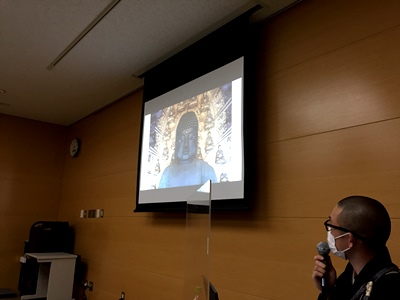
天然痘や天候不順で人がバタバタと亡くなり不安定だった時代に、大仏さまは造立されました。
その造立には、当時の日本の人口の半分が関わったとされています。
「みんなで協力して 苦しい時を一緒に乗り越えよう」という聖武天皇の想いから始まった大仏さまの造立。
その思いは後年にまで伝わり、たくさんの縁起が生まれました。
華厳宗の教えの中に、無尽縁起というものがあります。
縁は尽きることがない、という教えです。
この教えの象徴が、大仏さまなのかもしれません。
誰も予想をしていなかったコロナウイルスの拡大で、私たちの生活は大きく変わりました。
でも、大仏さま造立に関わった多くの人たちが、どんな風に手を取り合っていたか目を閉じて想像したら、なんだか元気がでてきました。
みんなで協力すれば、この危機はきっと乗り越えられるはず!
清水先生、本日は貴重なお話ありがとうございました!