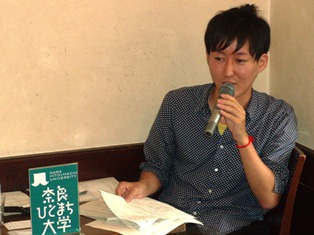今まで墨絵というものに縁がなかったのですが、奈良が好き!絵も好き!という単純な理由で申込みました。
教室になった、町屋を改装したというゲストハウスも雰囲気があり、素敵でした。

月与志先生はとってもおだやかな方で、作品のやわらかな線に表れているような気がしました。
でも、墨の付き具合や濃さ、紙に筆を置く時間によって、それは時に力強く荒々しく表現できるということも知りました。
1本の筆で、墨の濃淡と線の太さを変化させて描かれる先生の墨絵には、このデジタル化された社会に響くような無限大の可能性を感じました。
そして、それはまさに世界に誇れるアナログ時代の宝物をもった奈良から発信することに意味があるのだと思います。

小さいころから好きだったことが今の仕事につながっている、それは誰もが憧れることですが、簡単にできることではありません。
自分ができることは何だろうと考えて実行し、その活動によって多くの人が感動した時、価値あるものとなって仕事として成り立つのだと思います。

先生の貴重なお話の後、実際に目の前で素晴らしい飛天さまを描いてくださいました。
それから墨絵を体験してみましたが、線でも丸でも、描き始めると意外と夢中になりました(笑)。

このような方が奈良で活躍していることを誇りに思い、そして私も好きなことを続けていきたいという気持ちを強く持ちました。
素敵な時間をありがとうございました!

昨今、日本における食生活の乱れが問題視されている中で、健康志向が高まり、食の安全性などにも注目が集まりはじめたことで、昔から地域に伝わる伝統野菜を見直す動きも盛んになってきました。
それでも、生産効率の悪さのためか、味に個性があるためか、または特徴的な形のせいか、まだまだ大衆的な広がりをみせないのが現状です。
その折に、戦前から奈良で作られ守られ続けてきた伝統野菜18種にこだわりの野菜5種を含めた大和野菜についての紹介及び、それらを使った料理の試食会が行われる今回の授業を知り、普段手に取る機会の少ない野菜たちを身近に感じられる良い機会だと思い、参加させていただきました。

今回、試食で紹介していただいた野菜は、紐のように細長い“ひもとうがらし”や、紫色から熱を加えると緑色に変化する“紫とうがらし”、オーボエかと思うほど長くしっかりとした“大和三尺きゅうり”、まん丸で可愛らしいけどヘタのトゲが特徴的な“大和丸なす”など、初めて見る野菜ばかりでした。

一風変わった形のものばかりで味すらも想像つきませんでしたが、料理家の先生の手によって和風・洋風・デザートにと変化を遂げた野菜たちは、どんな料理にも合う、とても滋味に富む食材だということに気付かされました。
また、妙に長かったり、太かったり、見慣れない不格好なその形に愛着を覚えると同時に、そのような味・形になるに至った経緯や歴史なども頭の中で想像してしまいます。
まさに、胃袋だけではなく頭も満腹にさせてくれる、とっておきの野菜たちでした。

人の手によって丹念に、そして歴史を積み上げて育て上げられてきた歴史ある野菜たちは、生産者の思いを消費者に伝えるだけではなく、生産地の人にとっては誇りとなり、また外の人にとっては魅力にもなっていくものと思います。
今後も、このように昔から地域で守られ続けている野菜に注目していくことで、地域の歴史や魅力を再発見していきつつ、また、多様性のある日本の食文化を楽しんでいきたいです。
4月に奈良に引っ越してきて、たまたま『しみんだより』でこちらの講座の存在を知りました。
大和野菜とはどういうものか全く知らなかったので、興味があり申込みをしました。

授業のなかで、大和野菜にはどういう種類があるかを教わりながら、実際に野菜を使ったジュレやデザートをいただき、楽しく美味しく学ばせていただきました。

お土産もいただき、さっそく家でも調理をしてみました。
その後も、教えていただいた大和野菜をスーパーで見かけると、親近感をもって手にとるようになり、地元のものを知るきっかけになったと思います。
貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました!

授業当日、早めにお寺に到着したので、ちょっとぶらりと散策してみようとお庭に入れば、
初夏咲きのコスモスが迎えてくれました。

お庭はコスモスのほか、名前も知らない草花でいっぱいに満たされており、
それが歴史ある古いお寺の空気と交じり合って、
現実離れしたような、少し言い過ぎかもしれませんが
「此岸」と「彼岸」の間にいるかのような気持ちになったのを覚えています。
授業のはじめに教えていただいた香盛りは、私にとって初めての体験だったのですが、
丁寧に、一つひとつ手順を踏んでいく過程に、不思議と心が落ち着いていくような気がしました。
力を入れなさ過ぎると形が整わず、力を入れすぎると形が壊れてしまう灰を扱うというのも、どこか意義深さを感じます。
お香は、本来ならば仏さまにお供えするためのものですが、
うまく火がついて良い香りが漂うと、ついつい自分自身が喜んでしまいました。

できあがったお香をお供えし、みなさんで般若心経を唱えた後は、
いよいよ植物セラピーの講義です。
講義での副住職からのお話は、驚きとおもしろさの連続でした。

まさかお寺のコスモスを毎年すべて入れ替えてらっしゃるとは、想像にもしていなかったです!
入れ替えや育成の作業の様子をスライドでご紹介いただきましたが、その手間隙にただた
だ驚きました。
これまで、たくさんの拝観者の目と心を癒してきたであろうコスモス畑が、
このような多大な労力のもとに成り立っていたとは・・・。
そして、一般的に「コスモス」と聞いてイメージするお花だけではなく、
「こんなコスモスもあるんだ」とやはり驚いてしまうようなお花まで、
般若寺に咲くたくさんの種類をご紹介いただきました。

また、般若寺がコスモス寺と呼ばれるようになった由縁や、
大変だけれども受け継いでいかれようとする思いなどを、
お寺に従事されている方の言葉で拝聴できたのは、とても贅沢な機会だったと思いま
す。
今回の授業では、拝観で訪れただけではきっと触れることはなかったお話をたくさん聞かせていただきました。
そのせいか、改めてお庭を見渡してみると、少し景色が違って見えたような気がします。

秋になれば、教えていただいたたくさんの種類のコスモスに会いに、
そして仏さまにもご挨拶をしに、ぜひまた伺いたいと思います。
貴重な体験をありがとうございました。
以前、私は奈良のきたまちにあるお店でこんな質問をしました。「何故いつもこんなにお店がキレイなのですか?」お店の方は少し照れながら「・・・キレイな所をさらにキレイにする努力はやっぱりしてますね。」なるほどです。
こんなやりとりから「素敵な人をさらに素敵に伝えていくお仕事」をされてる方のお話が伺ってみたくて、申し込みさせていただきました。
先生は、NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」などの番組作りにも携わる築山卓観さんです。
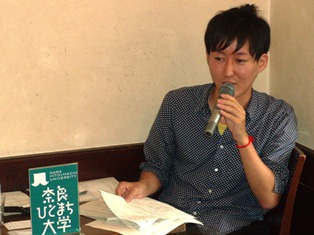
お話は「番組制作の流儀」というテーマを軸に、企画書作り→内容構成思案→撮影→編集→番組オンエア当日→視聴者さんの反響までを、丁寧に解説してくださいました。
興味深かったのは、ドキュメンタリーの取材でのお話。取材先の方に「声をかけるタイミング」に気を配るそうです。またカメラが回っているため、更に気を付けるとのことでした。また取材は現場が勝負、「構成を決めすぎるとそれ以外の大事なものを現場で見落としてしまうから」だそうです。このふたつのお話はハッとさせられました。
築山さんの「伝える情熱」にノックアウトされた貴重な時間となりました。

最後に今日の授業でいちばん胸に響いたこと。
「番組制作は共感できることが大切。
いかに普遍性を持たせられるかです。」
築山さん、ありがとうございました。
奈良ひとまち大学のスタッフのみなさまありがとうございました。
この授業がきっかけでクラスメイトができました。後日奈良で再会して授業について感想を話し合えたことも嬉しかったです。