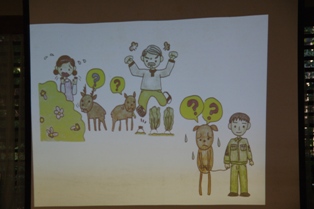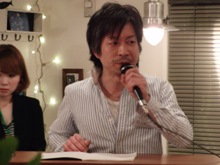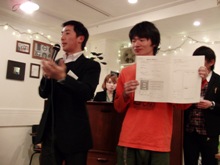姉に誘われ、
初めて奈良ひとまち大学の授業に参加させていただきました。
「今、話題の宿泊スタイルって?」という
タイトルに惹かれ、わくわくしながら授業に臨みました(^^)
学生の方々は思っていたより若い方が多く、
ご夫婦で世界一周された方など、
様々な経験をお持ちの方が集まっていました。
授業は実際のゲストハウス
JR奈良駅近くの「遊山」で行われました。

みんなで自己紹介をしてから、一周して見学。

私はゲストハウスを利用したことがなかったのですが、
木と畳の良い匂いがして、
近所に住んでいるけど今度一度泊まりに来ようかな、
と思ってしまいました。
先生は「遊山」のホスト、清重さん。
「遊山」の由来は「物見遊山」から来ているそう。
名前を決めるとき、「きよしげストハウス」という案も
出ていたみたいです(笑)
ゲストハウスを開くとき、
そのとき泊まったいろんな人々が
互いに話すことができるように、と
大きな広間をつくられたそうです。
そんな大広間での授業は、
いろんな質問が飛び交い、本当に和気あいあいという感じでした。
温かいオーガニック茶をいただきながら、
ここだけの裏話もたくさんお聞きすることができました♪

最後、私の姉の
「ゲストハウスを開いて良かったと思うことは?」
という質問に、
清重さんが
「偶然同じ日に宿泊したお客さん同士が
仲良くなって飲みに行ったりするとき。
特に日本人と外国人のお客さんだったりすると、
日本人がこの国の良さを生き生きと紹介していたりする。」
と、嬉しそうに答えてくれました。
確かに、こんなふうに間接的にでも
人と人との出会いを提供できるお仕事って本当に素敵だな、
と感じました。
人は、人と人との関わり合いのなかで生きていて、
人との出会いによって成長していくものだと思います。
ふとした出会いによって
自分の新しい可能性に気づくことも多いですよね。
お客さん同士を結び付けることのできるゲストハウスは、
ただの宿泊施設ではなく、
素敵な出会いの場なんだなーと思いました。

帰り道、姉とふたりで
いつか地元にゲストハウスを開こうね、
と約束しました。
単純かもしれませんが、本当に魅力的に感じたのです(^^)
奈良ひとまち大学のみなさん、
素敵な出会いをありがとうございました。
物心ついた時から奈良に住んでいて、鹿とともに暮らす街であることをちょっと自慢に思っていた私。他府県の友人を案内するのは、決まって奈良公園でした。
ある日、友人から「鹿に野菜の残りをあげていたら注意されちゃった。野菜の味を覚えた鹿は、畑を荒らすんだって。しかも荒らした鹿は鹿苑に閉じこめられて、一生出られないんだって!」というショッキングなことを聞いてしまいました。一生出られないなんて、なんて厳しい!
そんな折、鹿に関する授業があると聞き、その真相を確かめるべく参加することにしました。
授業をしてくださったのは、「奈良の鹿愛護会」の方。彼らが鹿の気持ちを代弁するという形で始まり、鹿と人間の共生の歴史から紐解き、「真の共生とは何ぞや?」ということを、面白くかつ真摯に教えていただきました。


鹿は国が定めた天然記念物でありますが、野生動物。
そんな彼らが街に下り人間と一緒に暮らしている・・・。これ自体が非常に稀有なことであり、生半可なことではないのです。
大昔から、鹿が田畑を荒らしたり角で人を傷つけたり、様々なトラブルが絶えず起こっていました。でも、先人たちの知恵と工夫で共生を維持してきたのです。
大きなことで言えば風物詩にもなっている鹿の角切りがそうだし、公園内で鹿せんべいを売ること、愛護会が発足してパトロールしてくれていることもその一つに数えられるでしょう。


本来なら本能に従い自由に生きる野生動物と、あえて街でともに生きることを選んだ私たちなのですから、そのためにはそれなりの努力と知識が必要なのです。
そう、鹿は「その辺にいるもの」ではなく、鹿とともに暮らすために何ができるのか一人ひとりが考え行動すること。
野菜をあげたらおいしい野菜を求めて鹿が公園の外に出てしまうことを想像しないといけないし、外に出たら交通事故の可能性も高くなります。
また、そこに花壇があればお花を食べるだろうし、食べられないためにお花を守る手段を講じないといけない。
鹿が単独で悪さをするのではなく、させないために、鹿とともに生きるための私たちの努力が欠かせないのです。
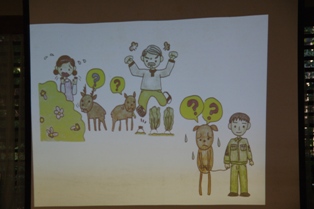
家の近所に鹿が来なくても、何も知らない観光客の方がお菓子をあげたりするのを止めることはできるし、具合の悪そうな鹿がいれば愛護会に連絡してあげることもできます。鹿と暮らしているのは自分であるということ、そのことをはっきりと意識することができました。
最後に、ケガをした鹿や畑を荒らしたりして捕まった鹿が収容される鹿苑を見せてもらいました。

ふだん石の柵が見えるばかりでしたが、中に入れてもらい全体を見渡すと、広い奈良公園のたった一角である鹿苑はやはり窮屈です。エサも新鮮な草ではなく干し草。たくさんの鹿たちが、出してほしそうにこっちを見上げています。ケガをした鹿は回復すれば出られますが、畑を荒らした鹿は同じ行動を繰り返すそうで、一生鹿苑で暮らすのは本当とのことでした。
奈良の鹿がずっとこの先も奈良のシンボルであり続けるように、ここに囲われた鹿がこれ以上増えないように、まずはこの話を周囲に広めることから始めようと思いました。
2月26日の夕刻、ならまちの「Cafe Flaska」さんで本日の授業が行われました。
白い壁の北欧風の店内にアンティークの小物がたくさんあしらわれていて、とってもおしゃれな、かつ心地よい空間でした。
参加者は20人程、4つの班に分かれて、まずはみなさんに自己紹介から。参加者は地元の方はもちろん東京や名古屋から来られてる方まで!比較的年齢層は高かったように感じました。
「Cafe Flaska」のオーナーさんから、お店を始めた経緯などのお話があり、なかでも一番驚いたのは、利用者の割合が、
観光客:地元のお客さん(常連さん) = 8:2 というお話。
ならまちという土地柄もあるんでしょうけど、予想もしない数字でした。
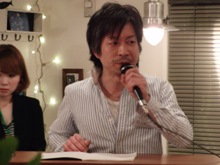

オーナーさんは、
「カフェというのはいろんな目的で利用できる場所だし、いろんなイメージがあって、いろんなカフェがもっとあっていい。」
「観光客の持っている“ならまちのイメージ”のなかに、こういうお店があってもいいんじゃないかな。」
ともおっしゃっていました。
そして、今回の授業のメインである、「カフェ発のまちづくり」の部分。
4つの班が「自分たちなら、奈良でどんなカフェを作るか!?」を考え、発表しました。
各班が、奈良の特産品である赤膚焼やいちぢく、飛鳥ルビー・三輪そうめん・大和地鶏・大和牛を使ったメニューを考えたり、情報発信の拠点となるカフェ、観光客の方が喜ぶ足湯のあるカフェなどなど、個性的でおもしろい新しいカフェの形を提案しました。



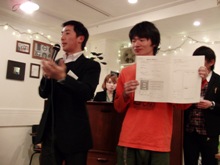
カフェとまちづくりの関わり方もホントに様々で、どんどん外に向かって発信していって、他府県からも「あのカフェに行きたい!」と思われるようなカフェを作るのも、まちの「価値」を上げることに繋がると思うし、逆に地元でひっそりと愛されるカフェもまた「地元愛」を育むまちづくりの形だと思います。
平城遷都1300年祭の契機もあり、奈良の街にも随分とカフェが多くなった気がします。
正直、カフェ飽和状態の気もしなくはないんだけれど、でも個性的で「また来たいなぁ。」と思えるカフェが多いのはいいことだと思います。
全てのメニューが終わってから、参加したみなさんで懇談会もありました。
参加者同士で、さらに意見交換やおもしろい情報交換などをして、楽しいひと時でした。

今回初めて奈良ひとまち大学の授業に参加したんですが、とても楽しかったです。新しい情報や人との出逢いはとても刺激になります。参加者のみなさん、スタッフの方々、「Cafe Flaska」のみなさん、ありがとうございました。
初めてひとまち大学の授業に参加をさせていただきました。
将来奈良に移住予定の私は、
自分の今までの経験を活かしたお商売を奈良でやりたいなと考えており、
知人が奈良ひとまち大学の授業を教えてくれたので参加することができました。
会場の「cafe Flaska」は、オーナーさんこだわりの北欧アンティーク家具が素敵なカフェ。
おいしい飲み物と軽食をいただきながら楽しく奈良のカフェについてイメージを膨らませ、有意義な時間を過ごさせていただきました。
まずはオーナーであるカントクさんから、今までの経歴と「cafe Flaska」開業の経緯などのお話。


その後のワークショップではグループに分かれて、
「奈良でカフェを開くなら?」というテーマで一つのカフェを作り上げました。

私は神戸出身の大阪在住で奈良の土地勘はいまいち無かったのですが、
他のメンバーの方々からユニークなアイデアが出て、
駅徒歩10分圏内で奈良の地域住民の憩いの場をコンセプトにしたカフェバーを考案。
・奈良の酒蔵をイメージし、蔵を改造した天井の高い店舗をゆったりと使用。
・インテリアは北欧テイストの落ちついた空間。
・夜はライブにも使える
・大和野菜のベジタリアンメニュー、郡山名産のいちじくのスイーツを提供する。
などでプレゼンすることになりました。

他のグループのプレゼンも、廃業後の銭湯を活かした足湯カフェや
奈良ホテルの雰囲気をテーマにしたラグジュアリー系カフェなど、地元の持ち味を存分に活かしたユニークなものが多くありました。
そんなみなさんのプレゼンのなかで私は、お茶・陶器・果物など奈良にはたくさんの名産があることを知りました。
奈良にはこんなにアピールポイントがあるのに、
なぜ関西人の私ですら知らないことが多いのかしら。
それにはアピールをしない保守的な奈良の県民性が関わっているのかもと、ふと思いました。
奈良の県民性を皮肉った言葉に「大仏商売」という言葉があります。
観光客が来るに任せて、受動的姿勢で商売をすることを意味します。
(*諸説あるようですが、この使われ方が一般的ですね。)
これを聞いた当時に、私は思いました。
京都なら観光客数の規模や経済効果を見ても観光客相手のお商売は並べて入れ食い状態でまだしも、「奈良はもっと元気があっていい!」という思いがあって、
更に経済的発展を望むのであれば、本当にもっと頑張ってもいいんじゃないかな、と。
奈良にとって「大仏商売」は町の活性化の明らかな障壁なわけで、
今の若い世代が、今の時代に合ったやり方で町を支えていくべきなんだと思います。
少なくとも「大仏商売」は今の奈良に合ったやり方ではないのは誰もが理解しています。

ここ数年の間でもちいどの通りやならまち周辺にはかわいいカフェや雑貨・服屋さんが続々と増えているように思います。
古いやり方を変えて新しい文化を創造している人が増えていて新たな魅力が増えつつあります。
奈良がどんどん変わり始めているということですね!
そしてこうして奈良の新たなカルチャーを広く紹介する授業を
開催しておられることは大変感心しております。
豊かな笑顔があふれるまちづくりに私も協力していきたい。
今回のワークショップに参加しいろいろ気付きをいただきました。
ありがとうございました。
3月12日の特別授業「奈良はボクらの宝物! ~みうらじゅんとイケてる住職が奈良を語る~」では、
東日本大震災の影響により、みうらじゅん氏が奈良に来られなくなったため、
急遽、先生を変更して開催いたしました。
先生を務めていただきました、平城遷都1300年記念事業協会の露口真広 様、
ならどっとFMの羽原亜紀 様、ありがとうございました。
さて、その授業のなかで、海龍王寺の石川住職からサプライズのプレゼントが発表されました!
なんと、海龍王寺に飾られている みうらじゅん氏 直筆の絵馬を、
特別授業に参加された方のなかから抽選で1名様にプレゼントしていただけるとのこと!!
アンケート用紙の裏面を使ってご応募いただいたところ、
145名のみなさまからの応募がありました。
そこで、当選者を決定するため、ユーストリームを利用して公開抽選を行うことにしました!!!
海龍王寺の石川住職による抽選の模様を、ユーストリームで放送します。
これまでに実施した授業の紹介や、これからの授業予定なども放送します。
ぜひチェックしてください♪
日時:2011年3月26日(土) 19:15頃 ~ 19:45頃
http://www.ustream.tv/channel/奈良ひとまち大学