
1984年生まれ。
大学在学中、訪れたロサンゼルスの雰囲気に影響を受け、奈良のイングリッシュパブで働き始める。
その後いくつかの店舗で働き、約3年間の修業を経て
2009年
「Tammy’s BAR」オープン
2012年
「もつ鍋屋うめ酒処はな」オープン
2014年
「世界のビールと日本の梅酒SEASONS」オープン
2019年
スナック「MOON」オープン

日時:2019年12月21日(土)13:30~16:30
教室:奈良女子大学(奈良市北魚屋東町)
●授業について
奈良~平安時代に多く用いられた甘味料、甘葛煎。廃れて原材料も製造方法も分からなくなった甘葛煎の再現実験を行い、幅広い校外活動も展開する、奈良女子大学の前川佳代さん。研究の成果や今後の展望を伺い、特製古代スイーツを味わってみよう。
☆スタッフブログ
「削り氷にあまづら入れて・・・」
→https://nhmu.jp/blog/info/14485
「古代スイーツに誘われて」
→https://nhmu.jp/blog/info/14542
【先生】
前川 佳代
(奈良女子大学 大和・紀伊半島学研究所古代学・聖地学研究センター協力研究員)
【参加費】
500円(飲食代)
【定員】
15人
【申込締切】
12月14日(土)09:00
※申込受付終了しました。
●レポーター:大津市在住 りい さん
奈良女子大学の向かいにある「街のお寺」、慈眼寺さんで、「ディープに学ぶ、慈眼寺のこと」に参加させていただきました。
一本道を歩きお寺に着くと、温かいお茶のおもてなしが・・・。
嬉しかったです。

お寺の副住職さんがまず「厄」の話をして下さいました。
「厄」という字は崖でひざまずく人の形から作られたそうです。
由来や私たちのイメージでは不吉な感じがしますが、崖のふちにいる訳ではないのでそれほど恐れなくていいとのこと。

よく「厄除」を私たちはしますが、厄除の本当の意味は「人生の節目の人が、これから先あまり大きな災いが起らないようにお願いすること」だそうです。
厄年は人生の節目で、先のことを恐れているうちは人間幸せだと、本当につらい人は先のことなど恐れたりできないとおっしゃっていました。

「厄」のありがたい話を聞いた後は、副住職さんの人生のお話をして下さいました。
仏教から離れてみようと思ってしたことが結局は仏教に繋がっていたという話がすごく印象に残りました。
教師もされている副住職さん。
ジョークも交えながらハンパないトーク力で、私たちにおもしろく分かりやすくお話しして下さいました。
そしてお寺の裏には市指定文化財の柿の大木があります。
樹齢400年の柿の木はとても立派で美味しそうな柿がなっていました。

普段できない貴重な体験ができてすごく勉強になりました。
副住職さん!ありがとうございました!
●レポーター:奈良市在住 あすぱ さん
「空が広く感じ、何もないがとても広い広場がある」
平城宮跡を初めて訪れた時の印象です。

しかし、本日の講座にはうってつけの場所でした。
本日の講座は、遠近法を駆使して面白写真を撮る。
遠近法にはカメラと被写体の位置関係が重要です。
また、カメラと被写体の間に何もない方が遠近感をなくすことが出来ます。
ウユニ塩湖の写真がよい例です。
PHOTO GARDEN 辻様から、遠近法を使った撮影には以下の4つが重要と教えて頂きました。
(1) 全体のピント
(2) 背景
(3) 声かけ
(4) モデルの演技力
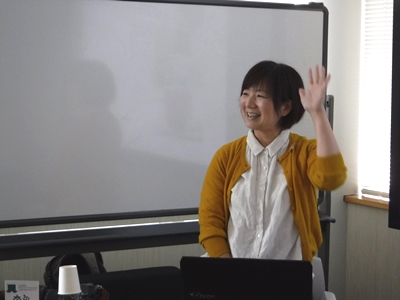
私が感じた
何もなく、広い。
この講座にはうってつけの場所だと感じました。
講座後、4人のグループに分かれ写真を撮りました。

私のグループは、かごから風船を持った人が飛んでいく写真がお題でした。
壁を背景とし写真を撮っていました。
しかし、壁を背景とすると飛んでいく感じがうまく出せない。
そう思いグループの仲間に空を背景にしてみないかと相談すると快く受け入れて下さりました。

改めて、かごの置く場所を変え、風船を持ってもらう人に「もうちょっと奥!もう少し右向いて!!」と声をかけ位置を微調整。

空に向かって飛んでいく写真を撮ることが出来ました。
その時の完成写真はinstagramでどうぞ
↓
https://www.instagram.com/p/B4HEN4XhpQs/
グループの人と話し合いをしながら写真を撮る楽しさ、遠近法を駆使した写真を撮る楽しさを知ることが出来ました。
●レポーター:奈良市在住 ゆめりん さん
ならまちの喧騒から離れた西の通りを歩き、路地を入った所に糞虫館はあります。
奈良ひとまち大学ののぼりが目印になりました。

扉を開けると白壁の部屋、急に明るい空間。
「糞」の持つ茶色い世界はありません。

メタリックな赤銅・黒・緑・青の美しく小さな糞虫たちが、宝石のように、カラフルなボール状のリングピローの上にちょこんと乗っているのです。

日本の糞虫だけでなく、世界の糞虫も。
大きな角を持ついかめしい糞虫も世界にはいるのですね。
展示を一通り見て2階へ。
中村圭一館長の講演が始まりました。
まず館長の自己紹介。
幼少期や中学・高校時代の昆虫との関わり方、学生時代の成績まで、サービス精神旺盛にお話ししてくださいました。
糞虫との最初の出会いは中2の昆虫採集。
大学時代にバックパッカーをして世界を歩いたことで、逆に日本の風景・環境の素晴らしさに気づかれたそうです。
自然に対するリスペクトが糞虫館の土台にあるのです。

金融機関退職後の「奈良県よろず支援拠点」(このような経営相談所があることも初めて知りました)での支援活動が資金獲得に繋がり、糞虫館オープンを実現されたことは、正に「情けは人の為ならず」ですね!
さて、いよいよ糞虫のお話。
「奈良は糞虫の聖地」
離島を含めて日本全体で160種の糞虫がいるうちの60種が奈良県、そのうち50種が奈良公園で生息しているとは驚きでした。
現在、奈良公園では鹿達が1日1トンもの糞をします。
それを糞虫は1~2日で、せっせと藁状、粉々にしてくれて、更にバクテリアが分解する。

「もし、糞虫が奈良公園から消えたらどうなるか?」
館長から問題提起があり、私たち学生は、一人ひとり頭の中でいろんなシーンを思い巡らせました。
(1)まず、奈良公園は糞だらけになってしまう。
(2)ハエが異常発生する。
(3)奈良公園に人が寄り付かなくなる。
(4)奈良の観光産業は衰退する。
説明を聞いて、糞虫が奈良公園の観光地化に大きく貢献していることがわかりました。
私たちのイメージするファーブル昆虫記のフンコロガシは、1つの糞を丸めて逆立ちして押して運ぶ「タマオシコガネ」です。
でも、奈良公園の「オオセンチコガネ」は前足で糞の破片を掴み後方へ進む、何往復もする働き者だということも知りました。

糞虫「オオセンチコガネ」の中でも、特に奈良公園のものは、美しい瑠璃色をしているので「ルリセンチコガネ」と呼ばれているのだそうです。
今や世界の人々から人気を集める奈良公園、これまで気づかなかった生き物たちと私たちの暮らしは繋がっているのですね。

早速、奈良公園に行って、青く輝くルリセンチコガネを探し「毎日ありがとう!」と言いたくなった、奈良ひとまち大学でした。
素敵なならまち糞虫館でのお話、中村館長ありがとうございました。