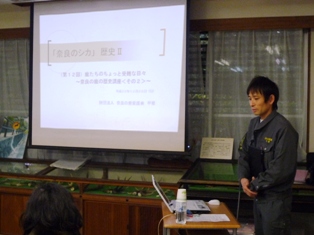今回は奈良市法華寺町にある海龍王寺にて、みうらじゅん氏から「イケ住(イケてる住職)」の称号をいただいた住職の授業。
最高気温が7℃の寒い日のお堂での授業となりました。

まずは、海龍王寺の歴史から。
元々、当所には飛鳥時代から毘沙門天を祀った寺院がありました。平城京造営の際、取り壊しや移転の憂き目に遭わず、逆に道の条割をずらして存続し(今でも奈良市役所から奈良ロイヤルホテルを越えて北に進んだ交差点がカギ型になっているのは、その名残だとか!!ヘェ~)、藤原不比等の邸宅や平城京の東北の鬼門を護ってきました。
海龍王寺は光明皇后が建立したのですが、名前の由来は、玄昉が唐からの帰り、遣唐使船で嵐の中を海龍王経を唱え、九死に一生を得て帰国したことから、聖武天皇から海龍王寺の名前と額を賜わったことによるとか!
また、玄昉は唐の武則天(則天武后)が各州に建立した大雲教寺に倣い、諸国に国分寺と国分尼寺を建立することを聖武天皇に進言するなど、我が国の仏教の発展に大きく貢献しました。
お話の後は、各自が境内を思い思いに巡り、自分にとっての癒しスポットを見つけるひととき~。
ひっそりとした佇まいはすべてが癒しスポットのようなものですが、私は、西金堂に安置されている国宝五重小塔の前で癒やされていました!この五重小塔は天平時代で唯一残っているもので、小さいながら、大変精巧にできています。また、門から外に出られませんでしたが、道路から門に至る参道の土塀も風情があって癒されます。


この後、住職に入れていただいたコーヒーをいただきホッとひと息つきながら、本日のメインテーマ「宗教は家庭の常備薬?」のコーナー。
まず住職から、昔からの宗教と家庭との関わり、現代の仏教における課題についてお話がありました。

昔は、「ウソついても神様仏様が見てるで!バチ当たるで!」など、日常のしつけや生活の中に宗教が自然に息づいていて、いわば「家庭の常備薬」のような存在でした。
しかし、現代はこうした教えが通じにくく、文明文化の発達とともに人々は横着になり、過程より結果が重視されるなか、教えの上でも特効薬が求められ、常備薬として安定から安定を説く仏教では人々の悩みや苦しみに応えきれず、特効薬的に不安定から安定を説く新興宗教などにすがる人々が多くなったりしています。
行基・法然・親鸞・日蓮など昔の僧侶は、自らの信念や個性を前面に押し出し、人々の信仰を集めていましたが、現代は宗派や教団の一員としての立場が重視され、個性を押し出しての宗教活動が難しくなっているとのことです。
住職のお話を伺っていると、「仏教の世界もいろいろ大変だなあ」と感じました。

その後の住職への質問は、「自殺しようとする人を仏教は救えるか?」「仏教をもっとわかりやすく教えてほしい」などといったものでしたが、住職は一つひとつの質問に、自らの体験談なども交えながら真摯に答えてくださいました。
住職は、仏教をわかりやすく伝える手段としてTwitterなどで情報発信されており、今回の質疑を通して、「1週間に一度、ブログで仏教をわかりやすく解説する。」と宣言されました!Twitterのアカウント名は@kairyuoujiですので、ぜひご覧になってください!
授業後、辺りは暗くなりましたが、いつの間にか参道に灯火が!


寒いなかでの授業となりましたが、住職のお話に心温まる一日でした。
3月は、第4土曜または日曜のいつもの授業とは別に、「特別授業」を開催します。
何が「特別」かというと・・・
☆特別その1☆
「生涯学習フェスタ2011」とのコラボレーションで開催します!
「生涯学習フェスタ」は、生涯学習センターと23館の公民館が一堂に会し、「生涯学習」を身近に感じてもらおうと、奈良市と(財)奈良市生涯学習財団が開催する一大イベントです。
授業当日、今回の教室となる中部公民館では、丹精込めて作られた力作の数々が展示されていたり、カレーや手作りこんにゃくなどの調理作品の販売があったり、喫茶コーナーや体験コーナーなどもあります!
授業終了後にぜひともお立ち寄りいただきたいと思います♪
☆特別その2☆
なんと、仏像ブームの仕掛け人(?)みうらじゅん氏と、みうら氏より「イケ住(イケてる住職)」と呼ばれる海龍王寺の石川重元住職による、夢の対談が実現!!
みうらさんは、独特な世界観が人気を呼び、イラストレーター・作家・ミュージシャン・ラジオパーソナリティーなど、幅広い分野で活動。2008年には、一大ブームを巻き起こした「国宝 阿修羅展」を記念し発足した「阿修羅ファンクラブ」会長に就任されています。
石川住職は、1989年に種智院大学を卒業後、仁和寺の密教学院にて修行。1991年より、海龍王寺住職を拝命されています。
「『イケ住』の称号に恥じぬよう精進いたします。仏教を、面白く、わかりやすく伝えたいです。」とのこと。
そんなお二人が、お気に入りの仏像や建造物など、奈良の魅力についてゆるゆる語ります。
参加申込の締切は、2月27日(日) 09:00 まで。
皆様のお申込をお待ちしています♪
申込はこちら ↓
【特別授業】 奈良はボクらの宝物!~みうらじゅんとイケてる住職が奈良を語る~
今年、一番最初に出会ったのは、元旦、夜明け前の道路の真ん中に佇む一頭の牡鹿でした。
互いに白い息を吐きながら「おめでとう!ほらっ道路の真ん中は危ないよ!!」と話しかけると、小走りで緑の中へ帰って行きました。日常の光景のなかに鹿との自然な共存の営みがある。この古都奈良に生息する鹿たちは、奈良に住む私たちにとってかけがえのない“誇り”だと思います。ここ、奈良市一帯には、現在1200頭余の鹿が生息していると言われています。
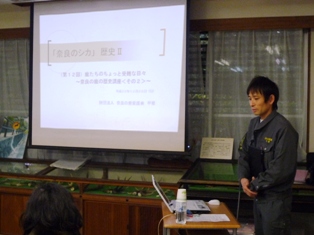
その生息の始まりと起源は神代の伝承にまで遡りますが、いにしえには人と神をつなぐ神鹿(しんろく)・神獣、明治以降の近代に至っては歴史の反動として、しばしば人間の田畑の農作物を食む害獣として乱獲冷遇された時期もあり、木柵に追い込まれた約700頭の鹿の数が一時は38頭にまで激減するなどの受難の歴史、戦争によるもの、そして議論・係争があったことをこの授業で知ることができました。

歴史は時として人間本位であり、しばしば自然の恩恵をもたらしてくれたその存在を忘れてしまいがちです。
人と神の存在を取り持つ大切な鹿たちのあり方も、人間側の一方的な論理でしばしば脅かされてきたことは、次世代への戒めとなり、将来にわたり記憶されるべきことでしょう。今日も鹿たちがそっと街角から私たちと歩みをともにしてくれていることを、忘れてはならないと思います。
鹿たちは人間のものであり神様のものであり、私たちにとって必要な伴侶なのです。


人と神様をつなぐ絆として、奈良市民、奈良を愛するすべての人々にとって、街角で出遭う可愛らしい鹿たちの存在は大変喜ばしいものであり、未来永劫この共生関係がさらに撫育されてゆくことを切に願わされます。
財政難による鹿の保護費不足への対策として、1672年から売られていたと記録にある鹿せんべいを紙の帯で巻くようになり、その売り上げの一部が保護費に活用されることになる・・・鹿せんべいを買うことにより、鹿の安全・健康面が守られ、人と鹿が触れ合う機会がもてるのですね。

ちなみに保護目的のために始まったラッパによる鹿寄せは、1953年以降ホルンへと代わり、その曲目はベートーベンの「田園」のホルンパートが吹かれているそうです。みなさんご存じでしたか?これがなかなか難しいのだとか。。。

最後に、長くなりましたが、奈良の鹿愛護会のみなさま、くれぐれもお怪我に気をつけてこれからも頑張ってください。
本当にありがとうございました。
奈良市の中心からそれほど離れていないにもかかわらず、なかなか訪れる機会が少なかった田原。
そこで伝統的なお餅つきを教えていただけるということで、初めて受講いたしました。

はじめに田原地区伝統芸能保存会の方から田原地区で古くから伝わる「千本杵餅つき」に関する簡単な解説を受けました。
お祝いの時には2升、3升の米をつき、それ以上の量をつく時はお葬式の時だともうかがいました。
お餅をつくという行為にもしっかりとした意味がある、このようなことこそが「伝統」なのだと感じました。



次に、屋外にて餅つき実習をしました。
その日は朝から雪が降っていたためとても寒かったのですが、地元のみなさまの歌うお囃しに合わせてお餅をつくと、次第に気分もからだもほかほかしてきました。
千本づきはひとつの石臼を囲みながら、数人がそれぞれ細い棒を持ってつくという方法です。


初めて見たときは、誰も混ぜ返す作業をしなくても大丈夫なのだろうかと思っていたのですが、次第にきちんとお餅になったのには驚きました。


しかし実際に体験してみると、お囃子や周囲の人たちと息を合わせながらつくというのはなかなか難しいものです。


つきあがったお餅は、みなさんと一緒にきなこやおろしをトッピングしていただきました。
最近はつきたてのお餅を食べるということがめっきりなくなってしまっていたので、そのやわらかさと美味しさに感動してしまいました。


後半は一般的な杵を用いてつきました。

遠慮がちに遠巻きで見学しながらも、何名かの方が体験されました。
私も少し体験させていただいたのですが、思っていたよりも杵が重くバランスが取りにくい印象でした。




そうしてできたお餅はみなさんに分配され、各々で小さな鏡餅へと成形しました。
この作業がなかなか困難でした。地元の方からアドバイスをいただくのですが、どうも不恰好になってしまい、何事も経験を積むことが大事なのだと感じました。


終りには、保存会の皆様にリクエストに応えていただいて「祭文」を少し披露していただきました。
「祭文」は県無形民俗文化財に指定されていて、浪曲などのルーツになったと言われている貴重な伝統芸能です。
実際に聴くことができてとても感動しました。

昔ながらの伝統文化をしっかりと継承され、魅力あふれる田原地区。
市内の人でもあまり訪れることが少ない場所ですが、知らずにいるのはもったいないと感じました。
今回魅力の端っこを見せていただいたので、これからもっと勉強して知人にも紹介したいです。
素敵な機会を与えてくださってありがとうございました。