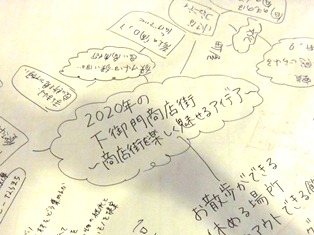Did you know the 東洋民俗博物館?
2014.05.30 | 授業info | by Staff
You know the 東洋民俗博物館?

東洋民俗博物館は、1928年(昭和3年)から奈良市あやめ池にある、れっきとした博物館です。

You know 九十九黄人(つくもおうじん)?
この仙人のような方が、九十九黄人さん。
東洋民俗博物館の初代館長をなさっていた方です。
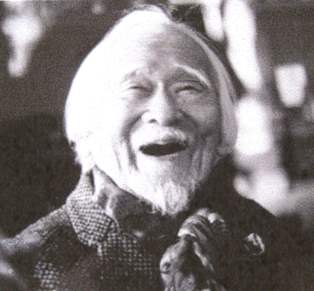
「世界超偉人伝説」「探偵ナイトスクープ」等のテレビ番組にも出演されたことがあるので、もしかしたらご存知の方もいらっしゃるかもしれません。
九十九黄人(本名:九十九豊勝)は、1894年(明治27年)の生まれ。
庶民の生活を理解する民俗学、とりわけ性の研究と蒐集に興味を持ち、各地の道祖神など性に由来する信仰に関心を持ちました。
また、おもしろいと思ったものは何でも収集し、博物館にはさまざまなものが展示されています。
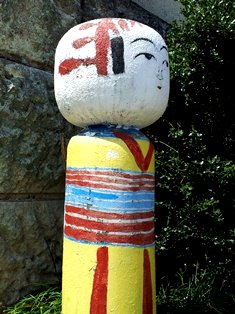
名前の「黄人」は、
黄色い人 → イエローマン → エロ―マン!
エロ―マン!
エローマン!
エローマン!
(サ〇ンの曲 イエ〇ーマン 〜星の王子様〜みたいですが)
自らエローマンをもじった黄人と称し、昭和の初期から民俗学(性)について研究されてきた方が・・・
おもしろくない訳がないッ!
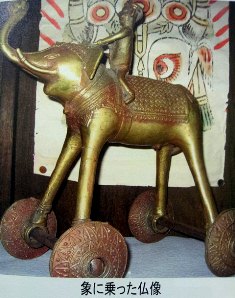
黄人さんは、こう仰られてたそうです。
「民俗学者の柳田國男は官の学者だったせいか、性に関するものがなく、その意味では自由奔放に生きた民の南方熊楠に魅力を感じた」
自らの研究する「性」という特異なジャンルの研究を突き進んだ黄人さんの、生き様を表したようなお話ですね。
時は過ぎ、性の解放も進み、性に関する研究も開放的になりました。
黄人さんは、生まれてくるのが50年早かったと言われています。
・・・
他にもエピソードは満載!
もっと沢山紹介したいのですが、詳しいお話は授業でのお楽しみ♪に取っておきます。

残念ながら、九十九黄人さんは1998年(平成10年)に103歳でお亡くなりになられており、お会いすることはできません。
(ご存命のうちにお会いしたかった・・・)
しかし、黄人さんは博物館に集めたものを残してくださった!
私たちはこれを見ることができるッ!

しかも、今回の授業では、その御子息、四男であられる、一般財団法人東洋民俗博物館 理事長 九十九弓彦(つくもゆみひこ)さんにお話していただけるんです!
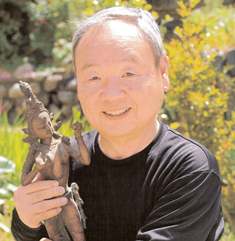
さらに!
今回は博物館所蔵の貴重な昭和初期のフィルム(DVD版)も見ることができるチャンス!!
(普段は見ることができなーーい!)
ん?
と思ったあなた。
んん?
と思ったあなた。
うふ~ん
と思ったあなた!
さぁ、ここから授業に申し込むのです!
↓ ↓ ↓
「ヘンテコでユカイ、それこそ民俗学!
~それいけ、東洋民俗博物館!!~」
http://nhmu.jp/class/18437
こんな機会なかなかないですよ!
あのお方も、こう申しております。
「チャンスは最大限に生かす。それが私の主義だ」
~Ch〇r Aznable~
(ask)