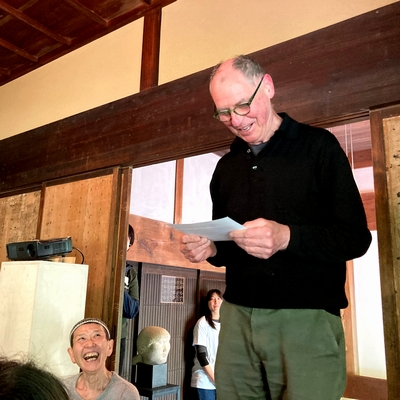藍より出でて
2023.04.30 | 授業 | by Staff
藍染の授業「わたしが藍の色にこめる思い ~藍師、染師という仕事~」にスタッフとして参加しました!
美しい色が生まれる現場「Indigo Classic」は、どんなところなのでしょうか。
教室に着いた時にまず感じたのは、藍の独特の匂い。
そして、ほぼ床一面にある板の下には、染液がたっぷり。
深さは1.5メートルで、温度はヒーターで常に21度くらいに保たれているそうです。

授業で聞いた小田先生のお話はたくさん勉強になったのですが、なかでも印象に残ったのは、草木染と藍染の違い。
草木染は煮出して焙煎するのに対し、藍染は酸化させて色をつけるとのこと。
酸化・・・つまりは空気にさらすということですね。

それが良く分かったのが、藍染体験を見た時です。
液に何度かつけて絞った後に水でよくゆすぎ、外でパタパタと手ぬぐいを風にたなびかせて乾かす学生のみなさん。
「液につけて乾かす」というシンプルさは、藍が元々庶民の色で、手軽に染められていたものだったという話を思い出させます。

模様をつけたい方は液につける前に輪ゴムで縛るとのことで、みなさん思い思いにデザインしていました。
濃淡や模様など、同じ液でも人によって個性が出るのが見ていておもしろい。

授業の詳しい内容は、「ひとまちレポート」をご覧ください!
「藍染め体験へ行ってきました」
http://nhmu.jp/report/39400
「藍染体験と先生の情熱に感動☆☆」
http://nhmu.jp/report/39427
染液に浮かんでいるものは、「藍の花」と呼ばれているそうです。
みなさんがすすいだ後のバケツの水にも、藍の花が早速浮かんでいました。

今回、スタッフは当然ながら体験ナシでした・・・(だってスタッフなんだもん!)。
藍の染液の手触りを味わうことも、どんな模様をつけようかと悩むことも、できあがった手ぬぐいをどう使おうかとわくわくすることも、できず・・・。
楽しそうなみなさんの様子を見てうずうずしていたスタッフ一行は、帰り際に小田先生に聞きました。
「私たちも染め体験できますかぁ!!?(半泣き)」
先生曰く、プライベートワークショップも行っているとのこと。
興味のある方は、Indigo ClassicのインスタグラムからDMでお問合せくださいね。
https://www.instagram.com/indigo_classic_nara
(もりぞー)