女性を輝かせてくれる平野さんとスムージー♪
2012.05.26 | 授業 | by Staff
甘い香りとポップなBGMが流れる店内。
“のぼり”を立てて、名簿を確認して・・・着々と授業の準備が進んでいました。

そこへ現れた今回の先生、平野奈津さん。
「初めまして」のご挨拶です。(失礼ながら、本番当日が初対面でした。)
ふんわりと、柔らかい雰囲気のある人だなぁ・・すごく可愛い人。
どんなお話をしてくださるのか、期待が高まります!

授業は、平野さんのプロフィールやこれまでに至った経緯などのお話から始まりました。
パワーポイントで出てくる写真もお洒落です♪
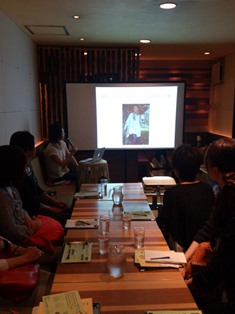
授業については、授業レポートをご覧ください★
平野さんに続け!きらきら輝く女性になるために。。。
仕事が軌道に乗り始めた矢先の妊娠、出産。
仕事に専念する夫を横目に、子育てとの両立に悩む日々。
そのご苦労を乗り越えながら、「女性をより自分らしく生き生きと輝くため」の仕掛けをたくさん作ってこられた平野さん。
そのパワーの源のひとつが、このスムージーだったのかな?


この日みなさんが召し上がったのは、オレンジ・パイナップル・りんご・バナナを牛乳で混ぜたスムージーでした。そこにオレンジとミントを添えて。
美味しそう~!!
ぜったい今度お仕事のない日にプライベートで来よう・・・。

「『子どもがいるから』『女だから』と自分にブレーキをかけていたのは自分。」
「困難があっても、働くと気づき、気づくと変わる。一歩一歩進んでいく。」
という平野さんの言葉。
とても印象的で、私自身も勇気をいただきました!
そんな平野さんの魅力に引き寄せられるように集まられた、学生のみなさん。
なかには、北海道から参加してくださった方も!
授業が終わっても、しばらく和やかにお話は尽きない様子でした。

(たぴ)













