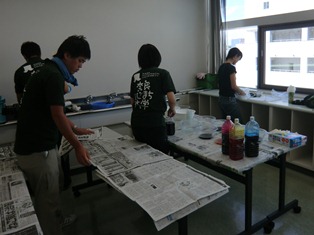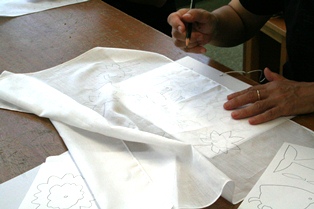おいしいコーヒーの秘訣!
2012.08.30 | 授業info | by Staff
おいしいコーヒーの秘訣みなさんは知っていましたか?
総務省の調査によると、奈良は家庭におけるコーヒーの消費量が日本一なんです。
そんなコーヒー好きのみなさんに、嬉しい授業ができました!
授業「一杯のコーヒーがつなぐ人とまち ~奈良で珈琲店をひらいた理由~」です★
教室となるのは、奈良でも多くのファンをもつ「珈琲豆蔵」。

扉を開けると、コーヒーの華やかな香りに包まれ、コーヒーが大好きな自分はそれだけでとても幸せな気分になってしまいます。
店内は木目調のシックな色合いで統一されていて、落ち着いた雰囲気。ゆっくり過ごすことができます。

珈琲豆蔵と言えば、そのこだわりは「コーヒー豆」です。
「コーヒーの原点は豆にあり」と、「豆」にこだわり、オーナーの北村さん自ら手間と時間を惜しまず、一粒一粒 豆を自分の眼と手で選別し、丁寧に焙煎されています。
そして、一番おいしい淹れ方で淹れたコーヒーを、お客さんに飲んでもらうことを心がけているとのこと。
なんだか、コーヒー豆がとても幸せに思えてきました。また、それを飲むこのできる、お客さんもとても幸せですね。
そんな、一杯のコーヒーができ上がるまでのストーリーや、コーヒーのもつ魅力、聴いてみたいと思いませんか?

そこで今回の授業は、珈琲豆蔵 オーナーの北村さんが先生です。先日の打合せで、授業の内容が決まってきました。
まず、コーヒーの種類・歴史を教えていただきます。
(コーヒーの木は、大きく分けて3種類の木があるそうです。)
また、大阪出身のオーナーが奈良で店を開いたことから始まった、コーヒーがとりもつ「縁」についてや、奈良の魅力について語っていただきます。
そして、自宅でも楽しく、もっとおいしくコーヒーを淹れることができる工夫なども紹介していただきます!

現在お店で出されているコーヒーは、ブルーマウンテン・キューバ(クリスタルマウンテン)・サントス(手摘み完熟)をはじめ、豆蔵自慢のブレンドコーヒーなど、約15種類が用意されています。
「当日は、いろいろなコーヒーを飲み比べてもらって、気に入ったコーヒーや気に入った焙煎具合を見つけてもらえたら・・・」
と、北村さんがおっしゃっていました。
参加費500円でいくつかのコーヒーを飲み比べることができるなんて、これはこの授業に参加された方だけの特典ですょ!

(かっぱ)