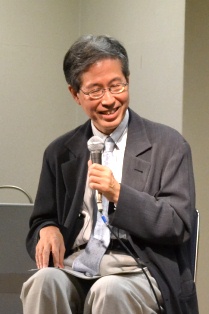ハピハピハッピー♪
2013.09.29 | 授業 | by Staff
9月29日、開校3周年記念特別授業「カブリモノで、笑顔をつくる ~作って、かぶって、奈良を遊ぼ!~」にスタッフとして参加してきました。
私が今回の授業でどれくらいハッピーになれたのかをハッピーメーター(100が満タンです)で表していきますので、参考にしてください。
授業は昼からでしたが、朝早くから教室の設営に取り掛かっていました。
(ハッピーメーター:10)
しばらくすると、チャッピー岡本さんが到着されて、教室に作品を並べ始めました。

作品が並べられていく様子を見ていると、ちょっとテンションが上がってきました。
(ハッピーメーター:20)

大体の作品が並んだ時は、なんとハッピーメーターは40になっていたのです!

教室の準備が終わると、お腹が減ってしまいハッピーメーターは15に下がってしまいました。

でも安心してください。
昼食を済ますとハッピーメーターは一気に65まで上がりました!
いい感じです!!
そうこうしているうちに、ついに開校3周年記念特別授業が始まったのです。
(ハッピーメーター:70)

素晴らしい授業の内容に、私のハッピーメーターは100になっていたのです!
授業の様子は、「ひとまちレポート」をご覧ください。
「かぶって あるいて」
http://nhmu.jp/report/16323
当日、私はカメラの担当だったので写真を撮るだけだと思っていたのですが、な・なんと!他のスタッフが「カブリモノを作ってきてもいいよ」と声をかけてくれたのです!
耳を疑いました。まさか、カブリモノを作ることができるなんて!ステキ!
(ハッピーメーター:120!)

それからの記憶があまりないのですが、気がついたときは自分が作った鹿のカブリモノをかぶっていました。
(ハッピーメーター:150!)
教室で記念撮影をした後は、カブリモノで街を練り歩きました。

みなさん素晴らしい笑顔で楽しそうに歩かれていました。

チャッピーさんの「chappy」は「change+happy」の造語で、「カブリモノを通して、みんなをハッピーにかえたい!」という意味が込められているそうですが、とりあえず私はハッピーになれました!
チャッピー岡本さんありがとうございました!

(じーあん)