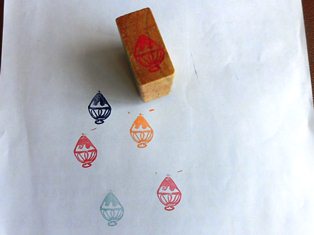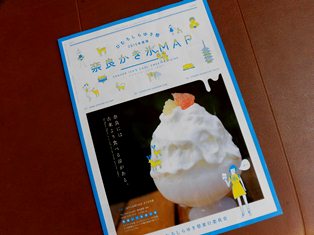学芸員さんとめぐった館
2016.04.30 | 授業 | by Staff
4月30日(土)、今回の授業「ヤング学芸員のお仕事事情 ~大和文華館をディープにご案内~」のキャンバスは、大和文華館。
歩いて10分ほどの所に以前勤務していた公民館があるにもかかわらず、初めてそこへ足を運びました。
学園前駅からの道中、ピンクや白のつつじが咲き誇る道を曲がると・・・

いや~びっくり!でした。
敷地がでっかい!
受付場所からは館が見えないんですよ。

授業開始とともに館内へと進み、ようやくその姿を目にできました。
授業の様子は、「ひとまちレポート」もご覧ください♪
「素敵な時空間」
http://nhmu.jp/report/25859
先生は、30代の学芸員・宮崎ももさんで、博物館で展示企画をしている方というよりは、ヘルメットを輝かせながら発掘現場で指揮しているといったイメージ。
(あくまで私のイメージです。失礼いたしました・・・。)
学芸員さんとしては若いほうだということで、授業のタイトルに「ヤング学芸員のお仕事事情」とついているわけですが、担当者の気持ちとは裏腹にご本人は「ヤング」という言葉に大分抵抗があったそうです。
(私のなかでは、意味は別として「ヤング」という言葉をもう使わないなぁと思ったり・・・。)
ヤングな感じは、確かに言葉や動きに表れていましたけどね。

その宮崎さんに導かれ、企画展示を鑑賞した後にはバックヤードへの扉が開かれ、いよいよ地下へ。
そこで衝撃的な部屋を発見!
それは、二酸化炭素が大量にストックされたお部屋。
なんでも、火災発生時の消火方法がお水ではなく二酸化炭素!なのだそうです。
確かに酸素がなければ燃えないしお水で消火すると収蔵品がダメになってしまいますものね。
なるほど、なるほど!
あってはなりませんが、万が一、大和文華館で火災が発生した場合はできるだけ早く館外へ脱出することをお勧めします(笑)。
ちなみに、通常はバックヤードへは関係者以外立ち入り禁止ですので悪しからず・・・。
(お菓子な世界)