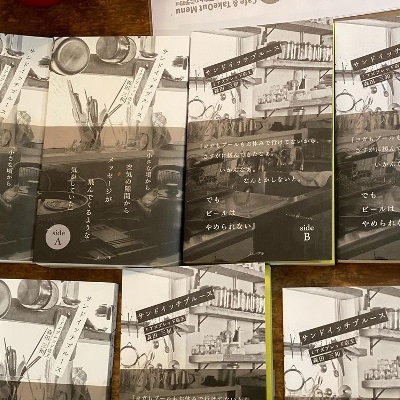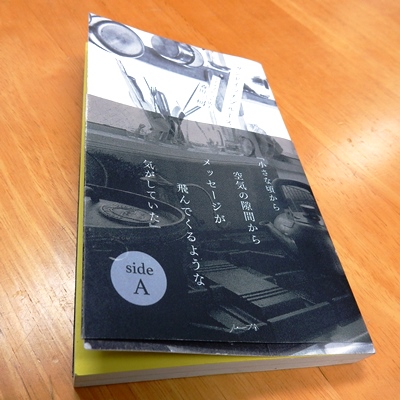漫画好き集結せよ!! ~授業に漫画家登場!~
2021.02.27 | 授業info | by Staff
みなさんは漫画好きですか?
私は大好きでございます。
漫画好きが高じて大学時代は4年間本屋でアルバイト。
就職したのも県内の大型書店でした。
その後、今の仕事になり、仕事で漫画に関わることがなくなったものの、こうやって漫画家さんと仕事をさせてもらうとは。
人生って不思議なものです。
滅茶苦茶話がそれました。
3月28日(日)の授業「57歳ではじめた『漫画』のお仕事 ~奈良を愛する漫画家、塔重五~」で取り上げるのは、奈良市在住の「漫画家」!
ペンネーム「塔重五」先生!

このペンネームから浮かんでくるのは、「五重塔」。
奈良の由緒ある建物からペンネームを考えるとは・・・。
ここから、かなりの奈良好きであることが伺えます。
しかも、「2019年まんが王国とっとり国際マンガコンテスト」で優秀賞を受賞しておられます!!

受賞作は「ドニチマン」。
ドニチ・マン?!
土・日・マン?!
土・日・萬!?
土曜日・日曜日にする麻雀のお話・・・?!
(しかも萬子限定?!?!)
(麻雀知らない方にとっては意味不明だろうな)
って冗談はさておき、本物の「ドニチマン」は授業で明らかになるでしょう!
さらに、同年に新刊コミック『紳士(ジェントルマン)と呼ばないで ~57歳ではじめてしまった漫画道~』を発売!!
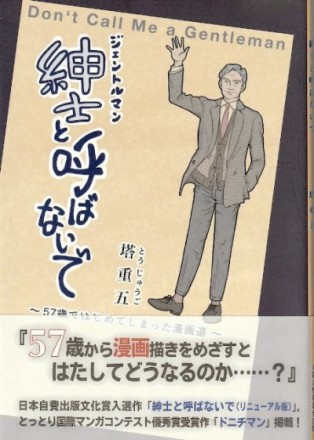
塔重五さんは57歳から漫画やイラストの仕事を始めました。
なぜ、その年齢で活動を始めたのか?
なぜ、それまで活動しなかったのか?
そのきっかけとなるキーワードが・・・
「デジタル」。
今は多くの漫画家が紙ではなくデジタルで作品を仕上げる時代。
そのデジタルが塔重五先生の活動を支えているそうです。
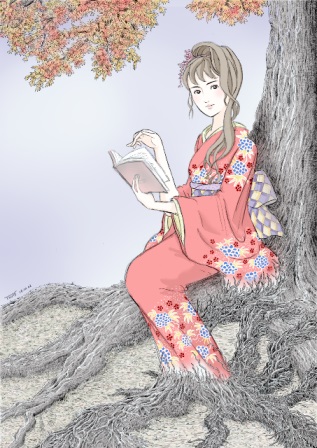
塔重五さんがどのような手段で作品を作っているのか、興味ありませんか?
そして、どのような考えを持って活動しているのか?
明かされる塔重五さんと奈良との繋がりとは?!
授業で全てが明らかになります!!
漫画好きなアナタ!!
漫画を描きたいと思っているアナタ!!
奈良好きなアナタ!!
漫画家「塔重五」先生の授業を楽しみましょう!!
教室はこちら、「Naramachi BookSpace ふうせんかずら」です。

まずはお申込みいただかなくてはなりません。
あの方もこう申しております。
「春の日や あの世この世と 馬車を駆り」
~「イノセンス」バトー(元は中村苑子の俳句)~
申込はこちら↓
http://nhmu.jp/class/35335
塔重五さんのホームページ↓
http://tou15.com/
(ask)