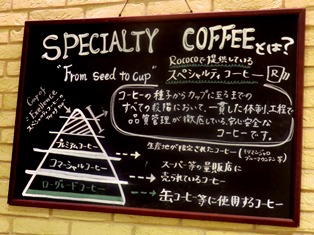春日大社の式年造替ふりかえり
2017.02.25 | 授業 | by Staff
2016年、春日大社にとって20年に1度の社殿の修築大事業・第六十次式年造替が行われました。
奈良ひとまち大学でも授業で何回も取り上げ、みなさんに式年造替を学んでいただきました。

奈良市に暮らし働く私たちにとって、これだけ歴史のある、連綿と続くこの式年造替を見ることは本当に貴重であり、大切なことだと思うんです。
(一生に何度も見れるものではないですからね。)
ん?過去の授業を思い出してみると・・・
!!!!
わたくし“ask”は一度も従事させてもらったことがない!
タイミングって言うか運って言うか・・・今まで従事スタッフとして春日大社にお伺いすることがなかったんですが、ようやく今回の授業「第六十次式年造替ログまとめ ~春日大社の式年造替を振り返る~」に従事させてもらうことができました。
授業の様子は、「ひとまちレポート」をご覧ください。
「もっと知りたい!春日大社」
http://nhmu.jp/report/27773
こういうのを「役得」って言うんでしょうねぇ。
お仕事で春日大社のお話が聞けて、御本殿にお参りできて、国宝殿まで見学させてもらえるって。
けど、スタッフはチョコチョコ動いて回らねばなりません。
記録・広報用として写真は撮らなくてはならないし、受講できなかった方のためにツイッターもあげなくちゃぁならない(今回“ask”は写真を担当)。

貴重な映像が流れていても、映像ではなく、映像を見ている学生のみなさんにカメラを向ける訳です。
となると、全てのお話を聞くことはできない。
(まぁ、そりゃそうか。)
外に出れば、歩いている先生&学生のみなさんの姿を撮影するために走って先を行かなければなりません。

まぁ、でもいいんです。
式年造替のお話を(所々)聞き、頑張って写真を撮って、雰囲気を味わうことができましたのでね。
そんななか撮影したお気に入りの1枚。

いい写真が撮れた時には“(´▽`) ホッ”とするものです。
(鹿さんがタイミングよくこちらを横切ってくれたんです!)
学生のみなさん、授業中ちょろちょろ動いているスタッフがおりますが、実はこんな内容のお仕事をしております。
うろちょろしてても怒らないでくださいね
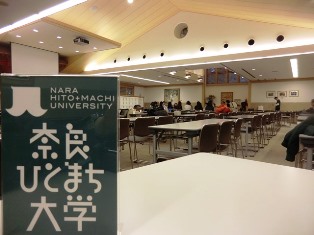
(ask)