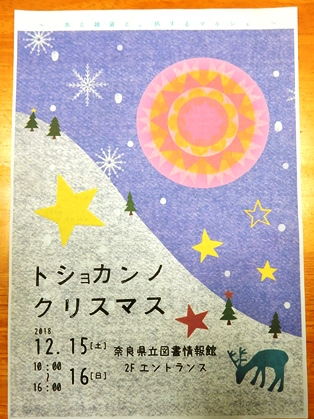ふわっふわの大きい綿菓子
2018.12.12 | 授業info | by Staff
12月22日(土)の授業「こだわり満載のポップな綿菓子 ~美容師が綿菓子店を開いたわけ~」のご案内です。
奈良に綿菓子専門店「Pamba pipi」ができたと雑誌で見てから、綿菓子が大好きな私としてはずっと行きたかったのですが、なかなかタイミングが合わず、やっと行けたのは開店から1年が経とうとしているときでした。
「夢CUBE」の裏だと聞き、夢CUBEを抜けて・・・
一瞬、「あれ?どこ?」と思ったら、すぐ左手にあった!
店先にかわいい綿菓子がいっぱい並んでいるのが目印です。

ドキドキしながらお店に入ると、お店の中は甘い香りで溢れていました。
メニューを見ながら、どれにする?と悩む。
種類が多すぎてなかなか決められない・・・

メニューを見ると、梅酒や酒粕なんてのもある。
こちらはアルコールが入っているとのことで、車で来たので断念。
ほうじ茶やチョコミントもある!
そのなかから、ちょっと変わり種の黒ごまきなことトマトをチョイスしました。
綿菓子は、顔が余裕で隠れるほどのボリュームです。
機械の前はガラス張りになっていて、作っている様子を見ることができます。
「こんなに大きい綿菓子、どうやって作るのだろう?」と見学していると、最後の方は手で綿菓子を巻きつけていました。

最後に粉を振りかけて、でき上がり!
「この粉なんですか?」と聞くと、フリーズドライのフレーバーだそう。
ふと店内を見渡すと、鹿のキャラクター「ROKU」ちゃんの絵が描かれた黒板とインスタの枠がありました!
ROKUちゃんの生みの親「amanojack design」は、以前、奈良ひとまち大学のフライヤーを作ってくださったんですよ~!
もちろん、授業の先生をしてもらったこともあります。↓↓
「『ROKU』、その世界的人気のヒミツ ~海外企業注目の鹿のキャラクター~」

さっそく、できたての綿菓子と記念撮影~♪
そしてそして、やっと実食!
「手がべたつくので」と、食べるための割り箸も用意してくださっています!
なんて素敵な心遣い~。

せっかくなので、お箸を使ってちぎってみます。
ふわっとした塊で綿菓子が取れて、いざ口に運んでみると、ほんとにふわっふわ。
口の中でゆっくり溶けて、フレーバーが口のなかに広がります!
黒ごまきなこもトマトも、ホンモノの味がします。
ん~なんておいしいの!!

店員さんにお話を聞くと、オーナーさんは、なんと美容師さん!
「ん?なんで?」ってことで後日、オーナーさんとお話をする機会をいただきました!
Pamba pipiオーナーの小林 聡さんは、東京で修業されていた美容師さん。
「なぜ綿菓子屋さんを始めたのですか?」とお聞きすると、美容院に来られた方が雑誌に載っていた祇園の綿菓子屋さんの記事を見て、「綿菓子屋さんいいな~」と呟いたのを聞いて、「よし、俺が作ろう」と思い立ったとのこと。
それから、「思い立ったが吉日」と、次の休みに祇園の綿菓子屋さんの視察に行き、その足で食品衛生責任者の講習に行くというフットワークの軽さ。
ね!おもしろい方でしょ?

お店はどんどん話題になり、今では2号店ができるほどの反響。
でも、ここまでくるには苦労もあったそうです。
美容院の経営とは違う、飲食店という難しさもあったそうです。
でも、「おもしろいところもたくさんある」とのこと。
授業では、美容師がなぜ綿菓子屋を開くに至ったのか、美容師から見る綿菓子屋について、存分にお話をお聞きしたいと思っています。
また、奈良生まれ奈良育ちの小林さんですが、学生時代や修業時代は奈良を離れていました。
一度外に出て「戻って来たからこそ見える奈良の良さがあります」と小林さんはおっしゃっていました。
奈良の魅力についても、みなさんと一緒にディスカッションする時間をもちたいと思っています。
もちろん、綿菓子の試食付ですよ!
カップ入りの持ち帰りができるタイプをいただきながら、お話を聞いていただきます。

お飲み物はご自分でおもちくださいね~!
ぜひお申込みください。
http://nhmu.jp/class/30929
(たかねぇ)