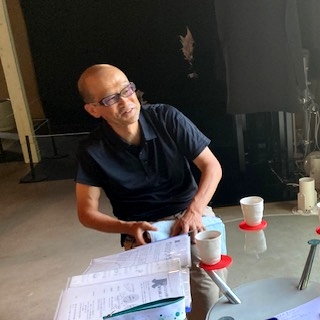人が集まる駄菓子屋さんの秘密
2024.12.14 | 授業 | by Staff
甘いデザートよりもスナック菓子が大好きな私は、今回の授業「二足のわらじで駄菓子屋をはじめた! ~『BOB’s_SPACE』オーナーの働きかた~」に、「駄菓子屋さんに行ける!」という嬉しい気持ちで従事しました。

教室に到着!
せっせと授業の準備を始めていると、「実は1か月くらい前にプロジェクターとスクリーンを設置したんですよ!」と松本先生。
なんと!!
急遽、まだ数回しか使っていないという綺麗な機材を使わせていただけることになりました。

学生さんが1人・・・また1人と、やってきました。
早く来た方は授業の開始時間まで、隣の駄菓子屋さんで早速いろいろなお菓子を購入しています。

レンタルスペースに戻ったら、机の上にルイボスティーとお菓子のセットが!
「寒いのでホットドリンクで温まってください」と、先生が配ってくださっていました。
気づいたら私たちスタッフの分まで!!
ココロもカラダも温まりました(#^.^#)

授業の様子は「ひとまちレポート」をご覧ください♪
「ちょっとしたこと、あったらいいなを実現する場」
https://nhmu.jp/report/42214
「奈良の魅力は親切な人が多いこと。困っている人が居たら放っておけない気質だと思う。」
「私のまわりに嫌な人はひとりもいない。」
「人のためにしていたと思っていたことが、実は自分のためになっていた。」
など、前向きな言葉が次々と出てくる松本先生。
普段からこういう気持ちで人と接しているからこそ、先生のまわりには人が集まり、良いご縁が生まれるんだろうな~。
まだお若いのに3人の子どもの子育てと両立していて素晴らしいなぁ~と、終始、感心しっぱなしでした。

授業が終わってからも、懐かしい駄菓子の話で盛り上がる人や、駄菓子やレンタルスペース以外に先生が取り組んでいるマルシェに興味を示し、何かタイアップできないかと名刺交換を始める人など、みなさん名残惜しそうでなかなか帰ろうとしません(笑)。
授業を通じて人と人がつながる、コミュニケーションの輪が広がる・・・スタッフとしてこの雰囲気がとっても嬉しいです。
これも奈良ひとまち大学の魅力のひとつですよね。
そういう私も学生の1人に共通の知人がいることが分かり、後片付けそっちのけで、ちゃっかりその話題で盛り上がっていましたが(笑)。
もちろん、帰りにはお土産の駄菓子を忘れずにゲットしましたよ。

(どす)