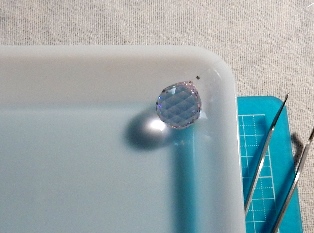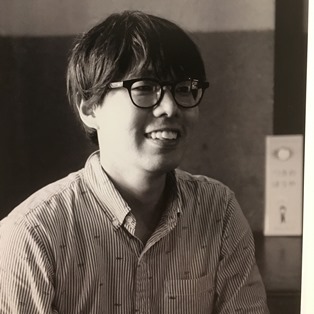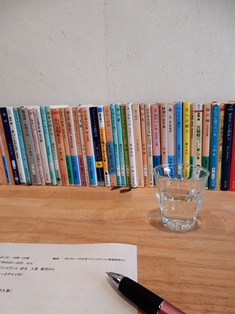2015年5月。
「ひとまちブログ」にて、ひとりの男性をご紹介したことを覚えていますか?
「世界を一周する男 2~もう既に3周目に入っております~」
https://nhmu.jp/blog/info/8524
実はその1年前、2014年8月にも紹介しています。
「世界を一周する男」
https://nhmu.jp/blog/info/6746
その男の名は「旅丸 sho」。
彼は世界一周(正確には三週目)の旅に出ており、「旅が終わって日本に帰って来たときには、奈良ひとまち大学で授業をしましょう!」とお願いしておりました。
それが今年の夏の予定でしたが・・・
しかぁし!その授業は今年、開催することができませんでした。
なぜかって?
彼が四周目の旅に出ちゃったからです(爆)。
では、旅丸 shoさんからコメントをいただいたので、どーぞ!
*******************************************************************
奈良ひとまち大学のみなさま、大変お久しぶりでございます。
「奈良から世界へ」と、大好きな奈良を2013年5月13日に出発し、既に3年以上が経過してしまっております、旅丸 shoと申します。
奈良ひとまち大学と出会い、帰国後に授業をという話を頂戴してから早2年・・・まだ旅を続けている次第でございます。
(授業を楽しみに待ってくださっているみなさま、お待たせして申し訳ございません。)
私は約1年で世界を一周し、この3年間で世界を三周してきました。
訪れた国数は100カ国以上。
訪問した都市は200を超え、旅を通じて知り合った友人は1,000人を超えました。
そんな私、旅丸 shoですが、今年の7月から世界四周目の旅をスタートさせました。
今回の旅のテーマは、【再会】。
旅で出会った様々な友人たちに再会を果たすということをテーマにして旅をしようと思いました。
現在、世界一周をしている日本人の数は、毎年数千人とも言われています。
その数千人の旅人の中でも、私はおそらく上位クラスの《不運な旅人》に違いありません。
ナミビアでの自動車事故。
キューバでの首絞め強盗。
マダガスカルでの逮捕。
ベルギーでの監禁。
ペルーでの骨折。
つい先日、中国の公安にも捕まりました。
もちろん悪いことをして捕まったわけではないのですが。
世界中、ありとあらゆる場所で私はトラブルに巻き込まれてきました。
日本で生活をしているだけであれば、こんなトラブルに巻き込まれることなんてないはずなのに・・・
普通であれば心が折れてしまうほどのトラブルの数々。
けれど、僕は旅をやめようと思ったことは1度もありません。

なぜなら、僕を支えてくれている人たちとの出会いがあったからです。
辛い出来事の後には、必ず素敵な出会いが用意されていました。
日本で生活をしているだけでは、決して知り合うことができなかった人たち。
私はそんな数々の出会いのおかげで、今も旅を続けたいと思えているんです。
私は彼らと別れの時に必ずこう言っています。
「See you again. また必ず世界のどこかで会おう。」
私はこの言葉に確かな意味をもたせたいと思ったんです。
「また会おう」という言葉はただの別れの言葉ではないということを。
もう一度再会するための約束の言葉なんだということを。
そう思い、再出発することを決めました。
私にしかできない旅を創り上げるために。
今回の旅のメインはヨーロッパとアジアになる予定です。
つい先日、さっそく嬉しい再会がありました。
彼の名前はオリバー。ドイツ人の学生です。
私とオリバーとの出会いは、2年前のブラジルでした。
私たちは出会ってすぐに仲良くなり、その後1ヶ月半ほど一緒に旅をする旅仲間になりました。

そんなオリバーと中国で再会を果たすことができました。
およそ1年半ぶりに再会し、僕らは以前と同じようにビールを飲み、笑いあいました。
彼はエメリック。
日本にいた時からの友人で、今回で3度目の再会になりました。
パリとロンドンのヨーロッパにおける主要2都市にて、いつもホームステイをさせてもらっています。
このブログもエメリックの家で書かせていただいています。

この後もすでに再会の約束でいっぱい。
外国人だけではなく、日本人の旅人との再会もあります。
「また会おう」の約束を果たした時、私と彼らに何が起こるのか。
今からそのことが楽しみで仕方ありません。
そして、こんなこともありました。
彼はトーマス。
私がジャマイカを旅している時に知り合ったスウェーデン人の男性です。
スウェーデンを旅している時には彼の家にも泊めていただいていました。
そんなトーマスなんですが、実は現在、旅人になって世界を旅している最中なんです。
再会したのはタイのバンコク。

そして、なんと日本にもやってきてくれました。
もちろん奈良も訪れてくれたトーマス。
日本のことを非常に好きになってくれ、約3週間、九州から関東までを旅しました。

トーマスは私との出会いがきっかけで、世界を旅することを決めたんだそうです。
旅を通じて誰かの人生を変えるきっかけになれたということは、私にとってすごく嬉しい出来事でした。
私は旅を人生の一部にしようと思います。
私を、そして旅を通じて誰かの人生をより素敵なものにすることができればと考えています。
そのために、まず私自身が旅の楽しさを誰よりも理解し、表現し、共有していこうと思いました。
世界一周ブログ《旅丸》
http://shutterbugtraveler.blog.fc2.com/
世界情報ブログ《TABIMARU.com》
http://www.tabimarusho.com/
こちらの2つのブログにて、私の日々の生活、そして今後旅をしたいと考えている方たちへの情報を書き綴っています。
ぜひ、ご覧ください。
奈良ひとまち大学での授業を通じて、みなさまの人生をより楽しく、豊かなものに変えるきっかけになることができればと考えております。
まだしばらく私の旅は続きます。
そして、素敵な物語はどんどん増えていくはず。
帰国時の授業で、みなさまに旅の素晴らしさをお伝えさせていただける日を楽しみにしております。

旅丸 sho
*******************************************************************
この授業は、またまたお預けです。
その分、どうか楽しみにしていただきたい。
きっとおもしろ、素敵なお話が聞けるはず!
それまで彼のブログを通じて、海外の人々との触れ合いとトラブルを一緒に味わってみませんか?
旅丸 shoさん、ちゃんと帰ってきてくださいね!
(ask)