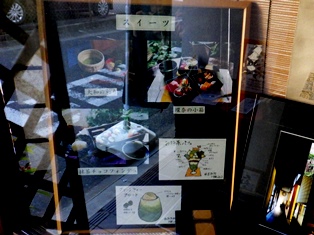2両連接バス「華連」に体験乗車できました
2017.12.16 | 授業 | by Staff
12月16日の授業「みんなの、いつものバス会社 ~奈良交通のこれまでとこれから~」に従事してきました。
教室である奈良交通株式会社平城営業所は、以前に勤務していた平城東公民館の近くで、前の道を「中はどうなっているのかな?」と思いながらよく通っていました。
普段なかなか入ったりすることのない場所が教室になっている時は、スタッフとして従事するのも楽しみです。

お天気を心配していましたが、雨はまだ少し先になりそうでした。
寒いなか、学生のみなさんは、バス・電車・タクシーなどで続々と集まって来ます。
欠席連絡をいただいた方以外、全員出席なのは、従事していて嬉しいことです。

授業の内容は「ひとまちレポート」をご覧ください♪
「軽やかで逞しい、バスの世界の奥深さ。」
http://nhmu.jp/report/29797
授業では、特に安全への取り組みについて熱く語られたので、これからも安心して奈良交通バスに乗れそうです。

室内での授業の後、運転手さんの乗車前の点検作業などを見学させていただきました。
バスの点検も多くの項目があり、ひとつひとつ丁寧です。

バスに乗って洗車機の中を通過しました。
右を見たり左を見たりで忙しいです。
車体が水洗いされ、さっぱり綺麗になりました。

次は2両連接バスの見学です。
良く目立つ黄色の車体で、横には丘を駆け上がるところをイメージした鹿が描かれています。
朝のラッシュ時など、駅に着いたら通勤通学の方がすぐに降りることができるよう、扉が大きく作られています。
2両合わせて130人も乗車できるとは驚きです。

所長さんの特別な計らいで、急遽、体験乗車をさせていただくことになりました。
前の車両に乗ったり、後ろの車両に移ったりしながら、みなさんたくさん写真を撮っています。

電車の連結部分とは違い、大きくカーブするところなど、初めての乗り心地でとても楽しかったです。

最後に、みなさんで記念撮影です。
スタッフとして行きましたが、私もとても良い体験をさせていただきました。
ありがとうございました。

(ぼちぼち)